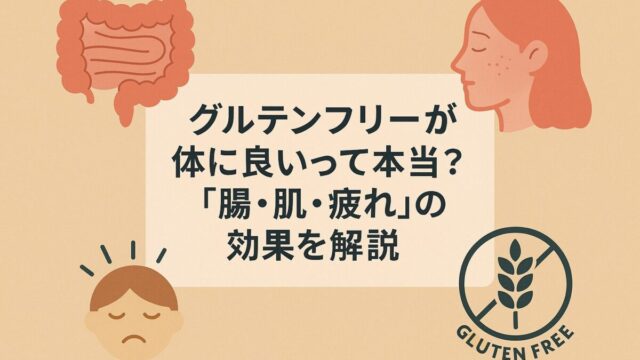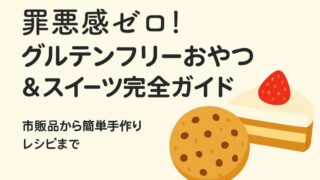最近、腸内環境の改善や体調不良の改善を目的として「低FODMAP(低フォドマップ)食」が注目を集めています。
まだ日本ではあまり知られていませんが、グルテンフリーと重なる部分や違いを理解することで、自分に合った食事法をより的確に選ぶことができます。
この記事では、低FODMAP食の基本的な考え方や特徴、グルテンフリーとの違い、具体的な始め方、そしてそれぞれの食事法が向いている人の特徴について、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
FODMAP(フォドマップ)とは?

FODMAP(フォドマップ)とは、「Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols」の頭文字を取ったもので、発酵性のオリゴ糖、二糖類、単糖類、そしてポリオールという短鎖炭水化物の総称です。
これらは小腸で吸収されにくく、大腸に到達すると腸内細菌によって発酵され、ガスや水分を発生させます。これが、腹部の膨満感、ガス、腹痛、下痢、便秘といった消化器症状を引き起こす原因となるのです。
FODMAP(フォドマップ)は主に以下の5つのグループに分けられます。
- フルクタン (Fructans)
- 特徴: 果糖が鎖状に結合したオリゴ糖。小麦、大麦、ライ麦などの穀物、玉ねぎ、にんにく、ごぼう、アスパラガスなどに多く含まれます。
- 症状との関連: お腹の張りやガス、便秘や下痢を引き起こしやすいとされます。
- 具体例: 小麦(パン、パスタ、うどん)、玉ねぎ、にんにく、長ねぎ、ごぼう、アスパラガス、チコリ、ピスタチオ、カシューナッツなど。
- ガラクタン (Galactans)
- 特徴: ガラクトースが鎖状に結合したオリゴ糖。豆類に多く含まれます。
- 症状との関連: ガスや膨満感の原因になりやすいです。
- 具体例: 大豆(豆腐、納豆は比較的低FODMAP)、レンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆など。
- 乳糖 (Lactose)
- 特徴: 牛乳や乳製品に含まれる二糖類。乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)が不足していると、乳糖不耐症として症状が出ます。
- 症状との関連: 下痢、腹痛、ガスなど。
- 具体例: 牛乳、ヨーグルト、チーズ(カッテージチーズ、リコッタチーズなど一部の高乳糖チーズ)、アイスクリームなど。
- 果糖 (Fructose)
- 特徴: 果物やはちみつに含まれる単糖類。ブドウ糖とのバランスが悪いと吸収されにくくなります。
- 症状との関連: 腹痛、下痢、ガスなど。
- 具体例: りんご、マンゴー、スイカ、はちみつ、高フルクトースコーンシロップ(異性化糖)など。
- ポリオール (Polyols)
- 特徴: ソルビトール、マンニトール、キシリトールなどの糖アルコール。一部の果物や野菜、人工甘味料に含まれます。
- 症状との関連: 下痢や腹痛を引き起こすことがあります。
- 具体例: アボカド、マッシュルーム、カリフラワー、サクランボ、プラム、桃、人工甘味料(キシリトール、ソルビトール、マンニトールなど)など。
これらの糖質は小腸で吸収されにくく、大腸で発酵することでガスや水分を発生させ、腸に負担をかけることがあります。
そのため、特に消化器系が敏感な人にとっては、これらが膨満感や腹痛、ガスの発生などの症状を引き起こす原因になり得ます。
低フォドマップ食とは、こうした糖質を一時的に除去または制限することで、腸内環境を整え、不快な症状を軽減しようとする食事法です。
低フォドマップ(低FODMAP)食品例
【低FODMAP食品(一部)】
- 野菜: じゃがいも、トマト、きゅうり、レタス、ほうれん草、ピーマン、にんじん、ズッキーニ、ナス、ブロッコリー(少量)、キャベツ(少量)など
- 果物: バナナ(熟していないもの)、オレンジ、レモン、ライム、ブドウ、メロン、キウイ、いちご、ブルーベリーなど
- 穀物: 米(白米、玄米)、米粉、オートミール(グルテンフリー表示のもの)、キヌア、そば(小麦粉不使用のもの)、コーンフレーク(小麦不使用のもの)など
- 乳製品: ラクトースフリー牛乳、アーモンドミルク、ライスミルク、豆乳(大豆分離タンパク質製のもの)、硬質チーズ(チェダー、パルメザンなど)など
- タンパク質: 肉、魚、卵、豆腐(木綿豆腐、絹ごし豆腐は少量ならOK)、テンペなど
- 調味料: 塩、こしょう、ハーブ、スパイス、オリーブオイル、酢、醤油(少量)など
【高FODMAP食品(一部)】
- 野菜: 玉ねぎ、にんにく、アスパラガス、カリフラワー、マッシュルーム、キャベツ(多量)、ブロッコリー(多量)、アボカドなど
- 果物: りんご、マンゴー、スイカ、洋梨、サクランボ、桃、ドライフルーツ、果汁100%ジュース(特に高果糖のもの)など
- 穀物: 小麦、大麦、ライ麦を含むパン、パスタ、クッキー、ケーキ、シリアルなど
- 乳製品: 牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム、カッテージチーズ、リコッタチーズなど
- 豆類: 大豆、レンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆など
- 甘味料: はちみつ、高フルクトースコーンシロップ、キシリトール、ソルビトール、マンニトールなど
- その他: カシューナッツ、ピスタチオなど
どんな人におすすめ?
以下のような症状や状況の方に、低フォドマップ食は特におすすめされます。
- 食後にお腹が張ったり、ガスがたまりやすい
- 腹痛や下痢・便秘などの消化器症状がある
- 過敏性腸症候群(IBS)と診断された、または疑いがある
- グルテンを除いても症状が改善しない
IBSだけでなく、原因不明の腸の不快感に悩んでいる方や、一般的なグルテンフリーで改善しなかった方にも有効なアプローチとなります。
グルテンフリー食との違い
| 比較項目 | 低フォドマップ食 | グルテンフリー食 |
|---|---|---|
| 避けるもの | 発酵しやすい糖質群 | グルテン(小麦・大麦・ライ麦) |
| 主な目的 | 腸内のガスや不調を改善 | アレルギーや消化トラブルの回避 |
| 対象者 | IBSや消化器系の不調を感じる人 | セリアック病やグルテン過敏症の人 |
| 対象範囲 | 小麦以外にも幅広く制限 | 小麦中心の制限 |
低FODMAP(低フォドマップ)食の始め方|3ステップで取り組もう

ステップ1|除去期(エリミネーション期)
2〜6週間ほど、フォドマップを多く含む食品を一度すべて除去し、腸の症状がどう変化するかを観察します。期間中は食事記録をつけると効果的です。
目的: 高FODMAP食品を一時的に完全に除去し、症状が改善するかどうかを観察します。
実践方法
- 高FODMAP食品のリストを参考に、これらの食品を徹底的に食事から排除します。
- 低FODMAP食品を中心に、バランスの取れた食事を心がけます。
- 食べたものと症状を記録する「食事日記」をつけることを強く推奨します。これにより、症状の変化を客観的に把握できます。
注意点: 栄養バランスが偏らないよう、様々な種類の低FODMAP食品を摂取しましょう。この期間は短期間に留め、症状の改善が見られない場合は専門家に相談してください。
ステップ2|再導入期(チャレンジ期)
目的: 除去期で症状が改善した場合、どのFODMAP成分が、どのくらいの量で症状を引き起こすのかを特定します。
実践方法:
- 除去期で症状が改善したことを確認した後、1種類のFODMAP成分を少量ずつ、数日おきに試していきます。
- 例えば、まずフルクタンを多く含む食品(例:少量の玉ねぎ)を摂取し、数日間症状の変化を観察します。症状が出なければ量を増やして再確認します。
- 症状が出た場合は、そのFODMAP成分があなたの「トリガーフード」である可能性が高いです。その成分の摂取は中止し、症状が落ち着いてから次のFODMAP成分を試します。
- この期間も食事日記は必須です。
注意点: 一度に複数のFODMAPを試さないこと。症状が出た場合は、その成分が原因であると特定できるよう、慎重に進めましょう。
ステップ3|維持期
目的: 再導入期で特定されたトリガーフードと、症状を引き起こさないFODMAP成分を理解し、それらを考慮した上で、多様でバランスの取れた食生活を送ります。
実践方法:
- 苦手なFODMAP成分は避けるか、少量に制限します。
- 問題なく食べられるFODMAP成分は積極的に食事に取り入れ、腸内細菌叢の多様性を維持します。
- 症状が安定していれば、徐々に様々な食品を試して、自分にとっての「許容量」を探っていきます。
- ストレス管理や十分な睡眠など、生活習慣全体を見直すことも重要です。
注意点: 低FODMAP食は永続的な除去食ではありません。不必要に多くの食品を制限し続けると、栄養不足や腸内細菌叢の偏りを招く可能性があります。
低フォドマップ(FODMAP)食のメリットと注意点
メリット
消化器症状の顕著な軽減
特に過敏性腸症候群(IBS)の症状(腹痛、膨満感、ガス、下痢、便秘)に悩む多くの人にとって、症状の劇的な改善が期待できます。
自分に合わない食材の明確化
再導入期を通じて、どのFODMAP成分が自分にとってのトリガーとなるかを具体的に特定できます。
選択的な制限が可能に
全てのFODMAPを永久に避ける必要はなく、自分に合わない成分だけを避ける、あるいは許容量内で摂取するといった、より柔軟な食生活が可能になります。
注意点
栄養バランスの偏り
除去期に多くの食品を制限しすぎると、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が不足する可能性があります。
特に食物繊維は腸内環境にとって重要であるため、低FODMAPの食物繊維源を意識的に摂取する必要があります。
食事管理の複雑さ
特に除去期は、食べられるものが限られるため、外食や加工食品の選択が難しく、食事の準備に手間がかかることがあります。
専門家のサポートが望ましい
自己判断で長期的に厳格な低FODMAP食を続けることは、栄養不足や腸内環境の偏りを招くリスクがあります。
医師や管理栄養士(特に低FODMAP食に詳しい専門家)の指導のもとで実践することで、より安全かつ効果的に進めることができます。
永続的な食事法ではない
低FODMAP食は、あくまで症状の原因となる食品を特定し、腸の不調を管理するための「ツール」です。症状が落ち着けば、再導入期を経て、できるだけ多くのFODMAP食品を食事に戻していくことが推奨されます。
これは、腸内細菌叢の多様性を維持し、長期的な健康を保つ上で重要です。
どちらの食事法が向いている?
| 状況・目的 | 向いている食事法 |
|---|---|
| 小麦でお腹が張る、でも乳製品も合わない | 低FODMAP食 |
| 小麦やパンを食べると不調がある | グルテンフリー食 |
| セリアック病・グルテン過敏症と診断済み | グルテンフリー食 |
| IBSや腸の不快感がある | 低FODMAP食 |
| 肌荒れや疲れ対策で小麦を控えたい | グルテンフリー食 |
まとめ|グルテンフリーと低FODMAP(低フォドマップ)食の違いと選び方

グルテンフリーと低フォドマップ食はどちらも腸の健康を意識した食事法ですが、対象とする成分やアプローチには明確な違いがあります。
- グルテンフリー:グルテンというタンパク質の除去に特化
- 低フォドマップ食:グルテンを含む広範な糖質の制限で腸内ガスや膨満感にアプローチ
グルテンフリーで改善しなかった方や、特に腸の不調が気になる方は、低フォドマップ食を試してみる価値があります。
ただし、どちらも自己判断では限界があるため、必要に応じて医師や管理栄養士のサポートを受けながら、自分に合った腸活スタイルを見つけていきましょう。